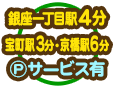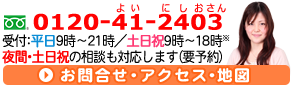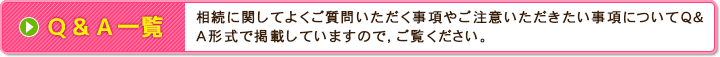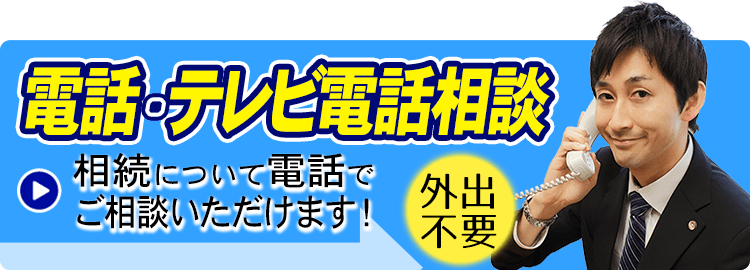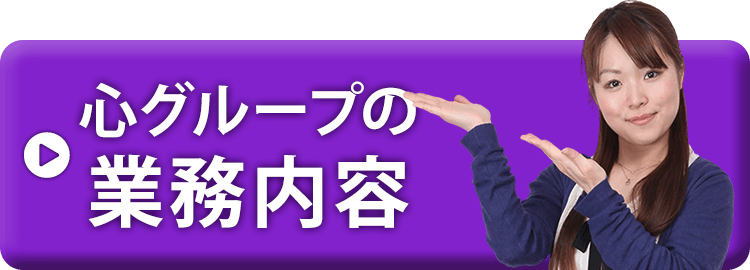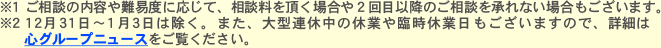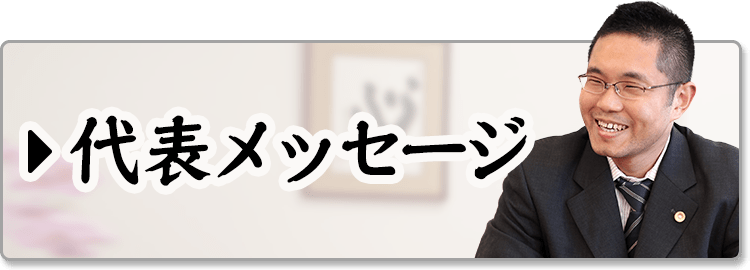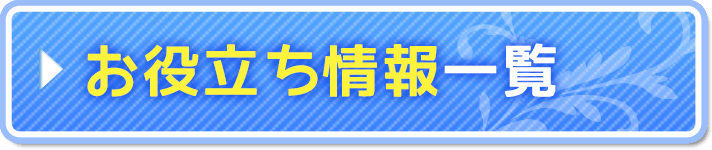相続時の預貯金の払戻し制度
1 預貯金の払戻しの必要性
以前は、相続開始後に、葬儀費用や相続債務を支払わなければならない場合でも、遺産分割が終了するまでは、相続人単独では預貯金の払戻しができませんでした。
そのため、事実上、口座が凍結される前に預貯金を払い戻しておくか、相続人自身の財産から支出するなどして対応しなければなりませんでした。
2 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度
2019年7月1日施行の改正民法により、遺産に属する預貯金のうち、一定額については、法定相続人単独で払戻しが認められることとなりました。
各相続人は、口座ごとに、相続開始時の預金額のうち、当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分の3分の1までは、金融機関から単独で払戻しをすることができます。
ただし、同一の金融機関からの払戻しの上限は150万円です。
この払戻しについては、家庭裁判所の判断を経ることなく行うことができます。
たとえば、相続開始時の預金額が1口座の600万円で、相続人が長男・長女の2名である場合、長男は、法定相続分(2分の1)の3分の1である100万円について、単独で払い戻すことができます。
制度の利用の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、払戻しを希望する方の印鑑証明書や本人確認書類などを、金融機関に提出する必要があります。
3 家庭裁判所の判断により払戻しができる制度
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所に申し立ててその審判を得ることで、預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることもできます。
ただし、生活費の支弁等といった仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
制度の利用の際には、家庭裁判所の審判書謄本、預金の払戻しを希望する方の印鑑証明書や本人確認書類などを、金融機関に提出する必要があります。