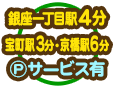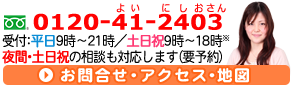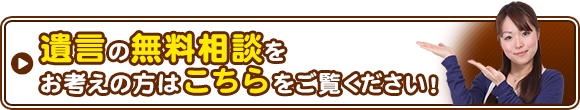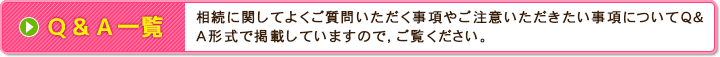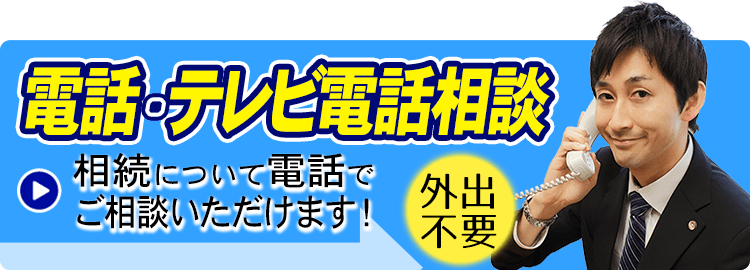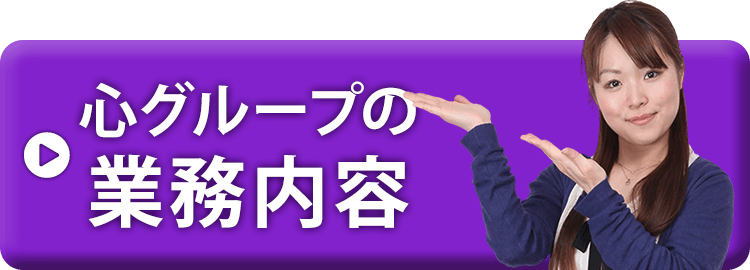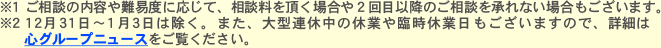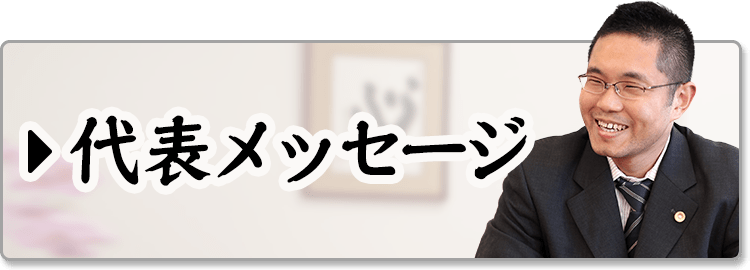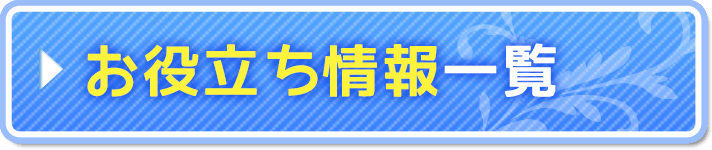公正証書遺言を作成する場合の流れ
1 公正証書遺言を作成する際の流れ
公正証書遺言は、3種類ある遺言のうちのひとつであり、公証役場という場所で公証人が公正証書の形式で作成する遺言です。
公正証書遺言には、汚損・紛失の可能性がほぼない、法的な不備が生じないなどの利点があります。
公正証書遺言を作成するには、財産の整理と遺言の内容の検討をしたうえで、公証役場での手続きを行います。
以下、それぞれについて具体的に説明します。
2 財産の整理と遺言の内容の検討
まずは、将来的に遺産となり得る遺言者の方の財産を整理します。
主なものとしては、預貯金がある口座と残高、不動産の登記情報、株式や投資信託の銘柄と評価額などを調査し、財産目録などにまとめます。
次に、誰にどの財産を相続または遺贈するかを決めていきます。
そのほかにも、相続人等に伝えたい事項があれば検討し、公正証書遺言の下書きをします(場合によっては、公正証書遺言の下書きとして自筆証書遺言を作成してみることもあります)。
3 公証役場での手続き
遺言の下書きまで作成したら、公証役場に連絡をとり、公正証書遺言を作成したい旨を伝えます。
そして、まず遺言の下書きと、遺産の裏付けとなる資料を提出します。
その後、公証役場側で遺言の下書きの確認がなされますので、指摘等があれば修正をします。
公正証書遺言作成の当日に公証人に支払う手数料の算定には、遺言に記載する財産の評価額が必要になりますので、評価額の根拠となる資料も提出します。
例えば、記帳済の預金通帳、不動産の登記と固定資産評価証明、有価証券の取引残高の資料などがあります。
公正証書遺言の内容が決まり、手数料の見積もりも終了しましたら、公正証書遺言作成の日時と場所の調整をします。
公正証書遺言を作成する場所は、基本的には公証役場です。
公証役場一覧は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。
参考リンク:日本公証人連合会・公証役場一覧
ただし、足が不自由であるなど、身体的なご事情等によって遺言者が外出することが難しいというような場合、公証人にご自宅や施設などに出張してもらうこともできます。
この場合、別途手数料の増額や、日当等が発生しますので、事前に公証役場に見積もりをしてもらいます。
公正証書遺言作成当日は、遺言者が公証人から遺言の内容等について説明を受け、証人2名の立会いのもとで、公正証書遺言が作成されます。