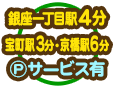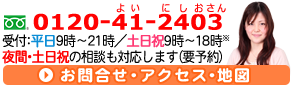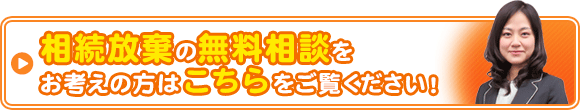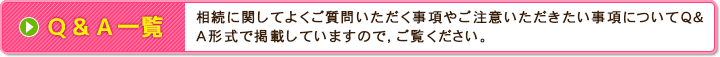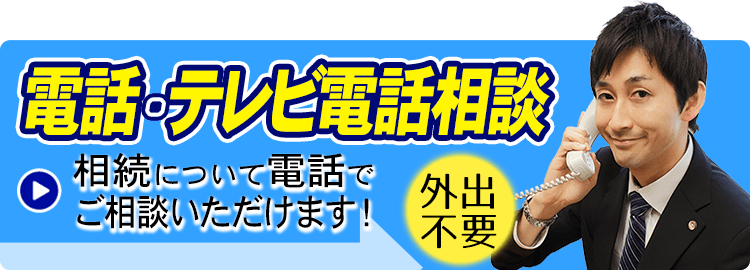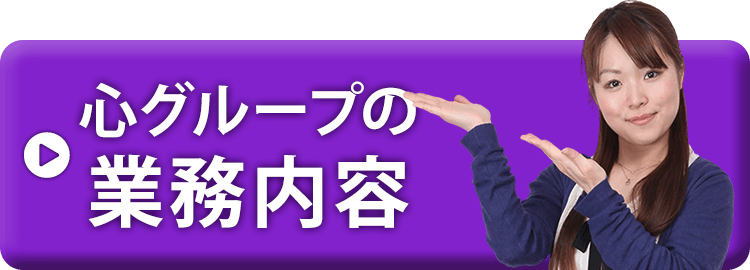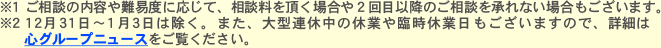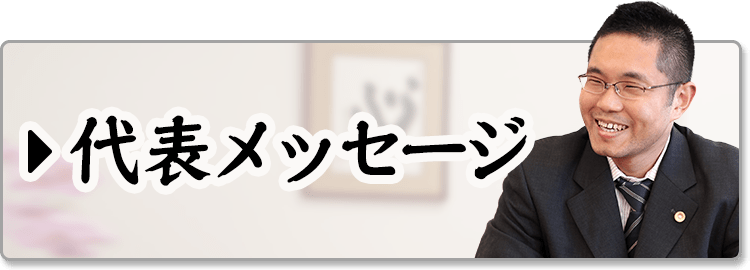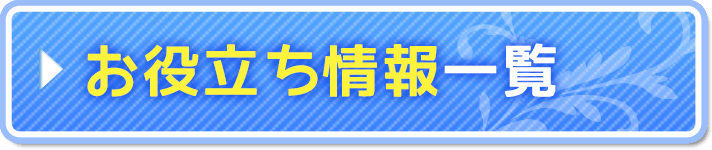相続放棄ができる期間
1 相続放棄ができる期間は相続の開始を知った日から3か月
⑴ 熟慮期間について
相続放棄は、相続の開始、すなわち被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。
この期間を、相続放棄をするか否かを検討する期間という意味で、熟慮期間と呼ぶこともあります。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるという強力な法的効果が生じますので、慎重な検討ができるようにするために、熟慮期間が設けられています。
熟慮期間中に、相続放棄をするかどうかを決定できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てを行い、熟慮期間の延長を求めることができます。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
⑵ 相続の開始を「知った日」からである点にご注意ください
熟慮期間は、相続の開始の日から3か月ではなく、あくまでも相続の開始を「知った日」から3か月です。
仮に被相続人が死亡してから3か月以上経過していたとしても、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内であれば相続放棄はできます。
被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知る日は同日になることが多いですが、何らかの事情により、被相続人と疎遠であった相続人は、被相続人が死亡してから1年後くらいに、被相続人の債権者等からの通知書面を受け取るなどして被相続人の死亡の事実を知るというケースがあります。
このような場合、もはや相続放棄ができないとなると、相続人に酷な結果になることから、熟慮期間は相続の開始を知った日から3か月とされています。
もっとも、裁判所としては、被相続人の死亡の日から3か月以内の相続放棄を原則的な扱いとしている印象があります。
そして、被相続人の死亡の日から3か月以上経過している場合に相続放棄をする場合には、事情を説明する資料等の添付を求めてくることもあります。
以下、被相続人の死亡の日から3か月以上経過している2つのケースについて、詳しく説明します。
2 被相続人の死亡の日から3か月以上経過している場合
⑴ 被相続人が死亡した日から3か月経過後に被相続人の死亡の事実を知った場合
典型的なケースとしては、数年~数十年音信不通であった親が、借金等を残したまま死亡していたというものが挙げられます。
被相続人の債権者が相続人を調査し、相続人に対して借金の返済を求める通知書面等を送付します。
相続人の方は、この債権者からの通知書面を受け取ってはじめて被相続人死亡の事実を知りますが、この時すでに被相続人死亡の日から1年程度経過しているということがあります。
この場合には、被相続人の債権者からの通知書面を読んだ日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をします。
その際、被相続人の債権者からの通知書面の写しを添付し、相続の開始を知った日から3か月以内の申述であることを示します。
⑵ 被相続人の死亡を知った日から3か月以上経過後に相続債務の存在を知った場合
被相続人が死亡したことを知ったものの、被相続人の借金等の存在を示すものがない場合には、通常であればわざわざ相続放棄をしません。
しかし、被相続人の死亡を知った日から3か月以上経過した後に、被相続人の債権者から相続人に対して連絡がなされ、相続人はこのタイミングで被相続人の債務の存在を知るということもあります。
このような場合、被相続人の債務について、容易には知り得なかったという事情がある場合には、例外的に、相続債務の存在を知った日から3か月以内であれば相続放棄をすることができることもあります。
この場合、家庭裁判所に対し、事情を説明する資料として債権者からの通知書面の写し等を提出するとともに、被相続人の相続財産を調査しても相続債務の存在を知り得なかった事情を説明します。
3 生前に相続放棄をすることはできません
相続放棄は、あくまでも「相続発生後」の制度です。
そのため、被相続人に借金があるからといって、生前のうちから相続放棄をするということはできません。
相続放棄をした場合の死亡退職金について 不動産の相続手続きが必要な理由