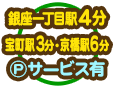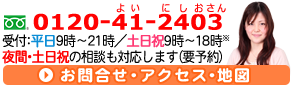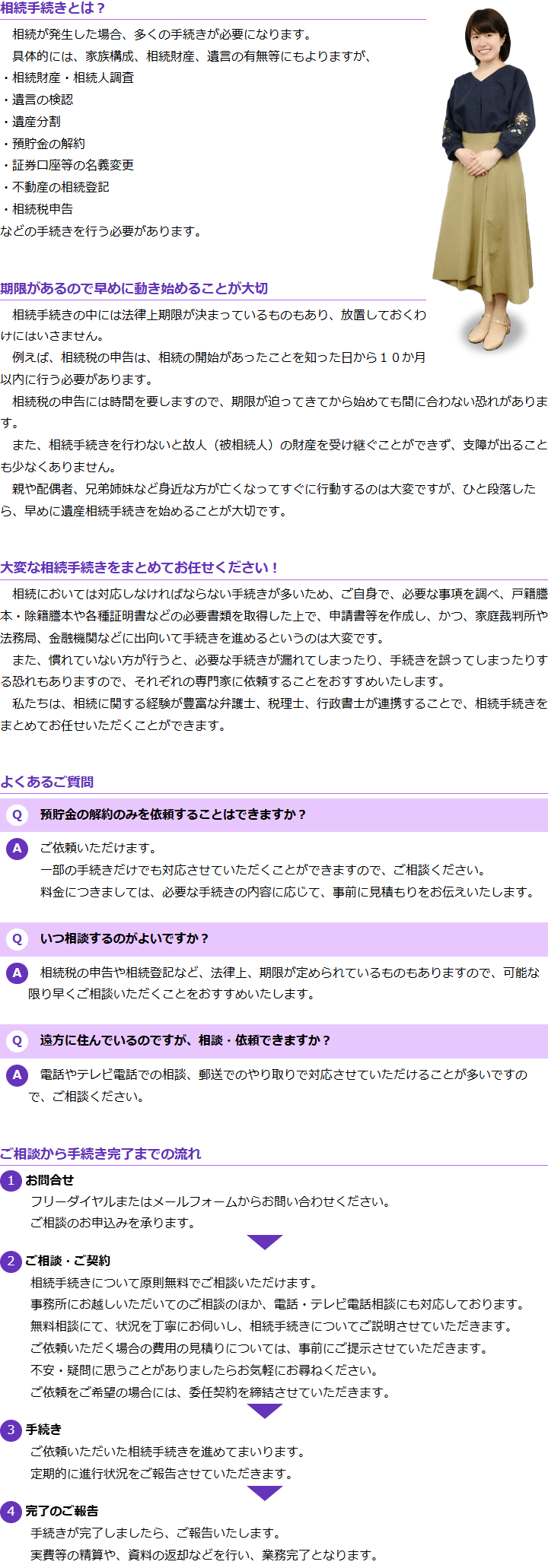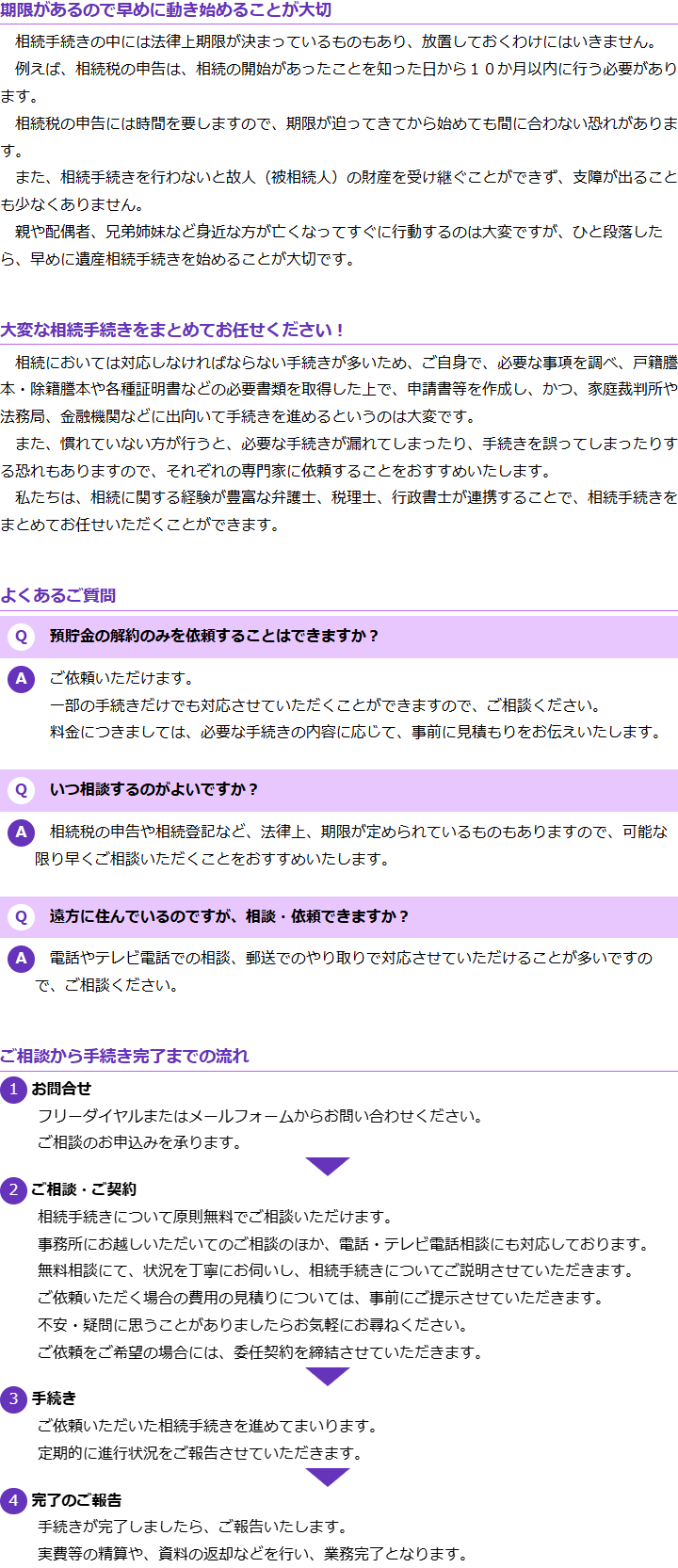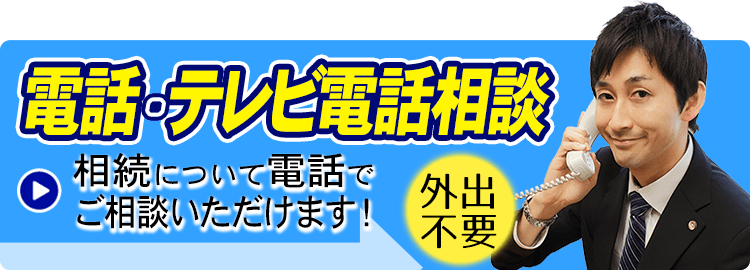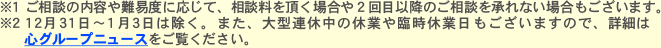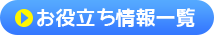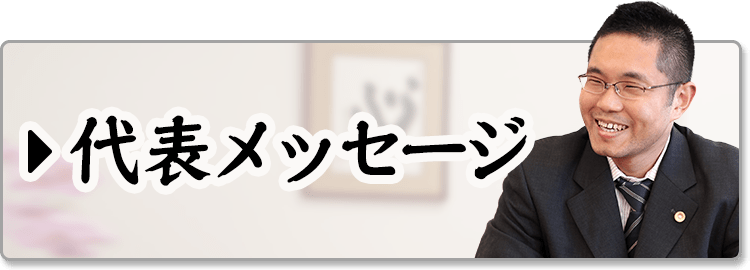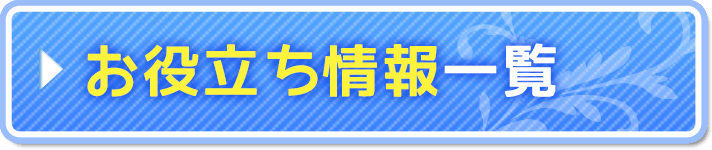相続手続き
相続手続きを専門家に依頼するメリット
1 専門家に依頼すると相続手続きをスムーズ進められます

法律上は、相続手続きは、相続人の方がご自身で行うことができます。
しかし、相続手続きには様々なものがあり、それぞれについて専門知識や実務的なノウハウが求められ、資料や書類作成などの作業も必要です。
また、手続きに不備があると、後になってトラブルになることもありますので、専門家でない方が相続手続きを行うのはとても大変です。
専門家に依頼することで、これらの問題を解消し、スムーズに相続手続きを進めることができます。
後述するような各相続手続きで行わなければならないことをまとめて依頼することができますので、相続手続きを専門家に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
2 主な相続手続きについて
代表的な相続手続きとしては、次のものが挙げられます。
①相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成
②(必要な場合)遺言の検認
③預貯金・有価証券の解約、名義変更
④自宅等の不動産の相続登記
⑤(相続財産評価額が一定金額を超える場合など)相続税の申告
以下、それぞれについて詳しく説明します。
3 各相続手続きにおいて行うこと
⑴ 相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成
相続手続きの前提となる作業として、相続人調査があります。
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本、および相続人の現在の戸籍謄本の収集を行います。
戸籍謄本類は、広域交付制度によって収集しやすくなりましたが、それでも市役所等での手続きが必要であり、専門家でない方にとっては簡単とは言い切れません。
遺産分割協議や相続税申告をするためには、相続財産を正確に把握する必要があります。
被相続人の預貯金通帳、有価証券残高証明書、不動産の登記や名寄帳などを元に、財産を整理するとともに評価額を算定します。
相続人と相続財産の調査が終了したら、どの相続人がどの相続財産を取得するかについて話し合い、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、法務局での不動産の相続登記や、金融機関での預金解約・名義変更で使用できるよう、適正な記載の仕方で作成することが求められます。
⑵ (必要な場合)遺言の検認
被相続人が自筆証書遺言を遺していて、法務局における保管制度を利用していない場合には、遺言の検認という手続きが必要になります。
遺言の検認をする際には、申立書を作成し、遺言の原本や戸籍謄本類を揃えて、管轄の家庭裁判所に申立てます。
その後、指定された日に家庭裁判所に赴いて検認手続きを行う必要があります。
⑶ 預貯金・有価証券の解約、名義変更
預貯金や有価証券の解約、名義変更手続きは、金融機関や証券会社によって異なることもあるため、個別の対応が必要になります。
また、金融機関によっては窓口でないと相続手続きができないこともあります。
いずれにおいても、戸籍謄本類と遺産分割協議書(または遺言)は必要になります。
⑷ 自宅等の不動産の相続登記
相続によって不動産を取得した場合には、相続登記をすることが義務付けられています。
相続登記をするためには、登記申請書を作成し、戸籍謄本類、遺産分割協議書(または遺言)、登録免許税等とともに管轄の法務局に提出する必要があります。
⑸ (相続財産評価額が一定金額を超える場合など)相続税の申告
民法上の相続財産、および相続税法上みなし相続財産とされる死亡保険金等の合計評価額が一定金額を上回る場合、相続税申告が必要になります。
相続税申告と納付は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人がお亡くなりになられた日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
また、小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用を受け、相続財産評価額が基礎控除額を下回る場合や、納付税額が0円の場合であっても、相続税申告は必要になります。