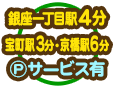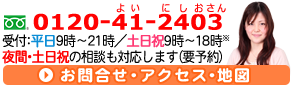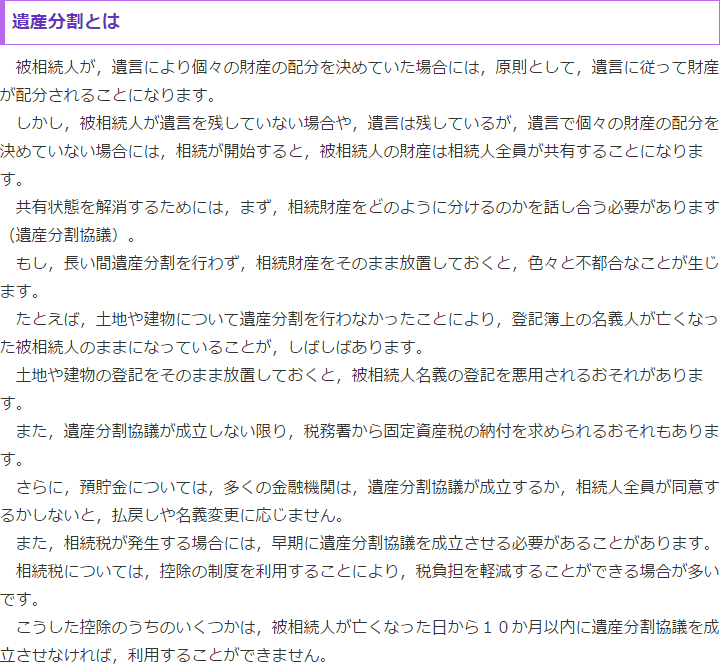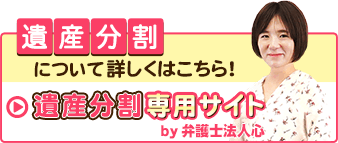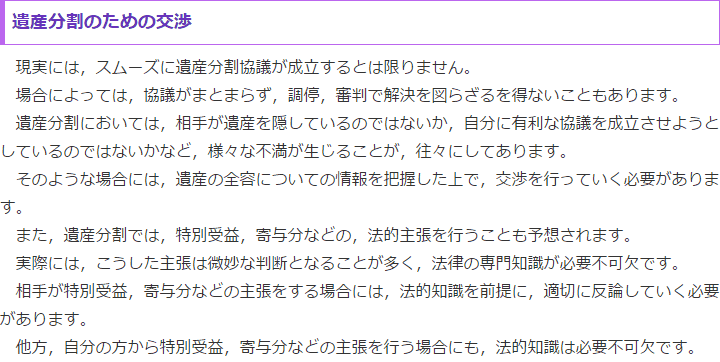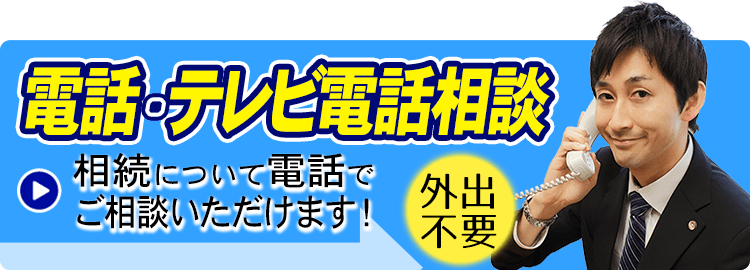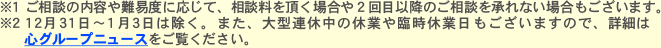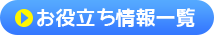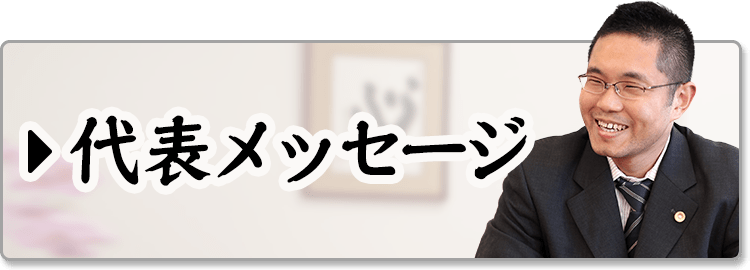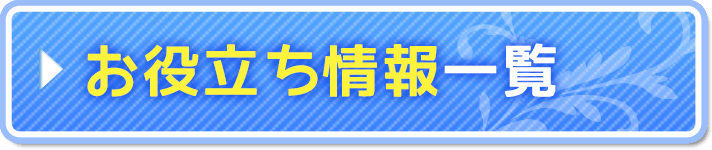遺産分割
銀座の事務所の情報
事務所所在地や詳しい地図などをご確認いただけますので、参考にご覧ください。銀座の事務所は複数の駅から徒歩圏内の便利な立地にあります。
遺産分割を専門家に依頼した場合の費用
1 遺産分割を専門家に依頼した場合の費用の概要

遺産分割を専門家に依頼したときの費用は、遺産分割に争いがない場合と、紛争に発展している場合とで異なります。
争いがない場合は、一般的には相談料、遺産整理・遺産分割協議書の手数料、実費がかかります。
紛争になっている場合には、基本的には相談料、着手金、報酬金、実費がかかり、調停を提起する場合には別途追加着手金と出廷費も必要となります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 遺産分割に争いがない場合
遺産分割について専門家に相談をした場合、まず相談料が必要になることがあります。
専門家によっては、初回の相談料が無料であったり、依頼を受けた場合には相談料無料としているケースもあります。
遺産分割に争いがない場合には、まずは相続財産の調査と評価を行い、遺産目録を作成します。
同時に、戸籍謄本類を収集して、相続人調査・確定をします(遺産分割は相続人全員で行わないと無効になってしまうためです)。
その後、相続人間で話し合って決めた遺産分割の内容を反映した遺産分割協議書を作成します。
これらの業務の手数料は、遺産の総額の1~2%であることが多いです。
そのほか、戸籍謄本類や相続財産を裏付ける資料を取得した際の自治体等に支払う手数料や、郵送費などの実費がかかります。
3 遺産分割の紛争に発展している場合
遺産分割で争っている場合、相談をする先の専門家は、基本的には弁護士となります。
この場合も、2と同様に相談料がかかることもあります。
遺産分割の紛争の場合には、着手金と報酬金がかかります。
着手金は、結果にかかわらず弁護士に支払う金銭であり、通常は獲得が想定される経済的利益の数%とされます(最低金額が定められていることもあります)。
報酬金は、遺産分割が終了した際に獲得した経済的利益に応じて支払う金銭であり、獲得した経済的利益の数%~十数%程度です。
そのほか、戸籍謄本類や相続財産を裏付ける資料を取得した際の自治体等に支払う手数料や、郵送費などの実費がかかります。
調停を提起せざるを得ない場合には、所定の書類を揃えて家庭裁判所に提出する必要がありますので、弁護士によっては数十万円程度の追加着手金が必要となることもあります。
また、調停の期日に弁護士が出廷する場合、出廷1回あたり数万円程度の出廷費と交通費が必要となります。
遺産分割調停の流れ
1 遺産分割調停の流れ

被相続人がお亡くなりになり、相続人間で遺産分割協議を行ったものの、話がまとまらずに争いに発展してしまうということはあります。
話し合いでは遺産分割協議を成立させることができない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。
遺産分割調停は、家庭裁判所への申立てをした後、期日と呼ばれる日に家庭裁判所で調停委員を介した話し合いを行います。
その結果、遺産分割の内容がまとまったら調停調書を作成して終了となります。
もし、ここでも話が平行線になったり、一切連絡に応じない相続人がいる場合には家庭裁判所による審判がなされます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 遺産分割調停の申立て
遺産分割調停は、調停の申立書を作成し、戸籍謄本類、相続財産目録、相続財産を裏付ける資料などを添付して、管轄の家庭裁判所に提出することで開始されます。
管轄の家庭裁判所は、遺産分割の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、相手方の住所地が遠方である場合には、期日に出席するための移動の労力も考慮する必要があります。
3 遺産分割調停期日
遺産分割調停の申し立てをすると、家庭裁判所が期日を設定します。
期日の日になったら、家庭裁判所に行き調停委員を介した遺産分割の話し合いを行います。
弁護士に遺産分割調停の代理を依頼した場合には、弁護士が期日に同伴することもできますし、弁護士のみが期日に出席するということもできます。
4 遺産分割調停成立または審判移行
遺産分割調停の期日や、調停外での話し合いで遺産分割の内容を決めることができたら、調停成立となり、家庭裁判所から遺産分割の内容を記した調停調書が交付されます(調停外で遺産分割協議書を作成し、調停を取り下げるということもあります)。
遺産分割調停をしても話が平行線になってしまうことや、一切連絡に応じない相続人がいて話が進まないこともあります。
このような場合には、調停を継続することは困難であることから、遺産分割調停は審判に移行し、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定します。
遺産分割協議書の作成の流れや注意点
1 遺産分割協議書作成の流れと注意点の概要

被相続人の方がお亡くなりなって相続が開始され、遺言がない場合には遺産分割協議を行う必要があります。
相続人間で遺産分割協議をし、誰がどの相続財産を取得するかを決めたら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成するうえでの主な注意点としては、相続人全員で遺産分割協議書の作成を行うこと、相続財産の情報は正確に記載すること、押印には実印を用いることが挙げられます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 相続人全員で遺産分割協議書の作成を行うこと
遺産分割協議は、相続人が全員で行わないと効力を生じないこととされています。
そのため、事前に相続人を調査しておく必要があります。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得することで調査することができます。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も収集します。
これらの調査で確定させた相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作ります。
3 相続財産の情報は正確に記載すること
遺産分割協議書には、どの財産をどの相続人が取得するかを、できるだけ具体的かつ正確に記載します。
例えば、預貯金であれば、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義を正確に記します。
不動産は、登記等を参照し、土地であれば不動産番号、所在地、地積、地目などの情報を正確に記します。
このようにしておくことで、財産を特定することができるため、金融機関や法務局での相続手続きを円滑に進めることができます。
4 押印には実印を用いること
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員で署名と押印をします。
このときの押印には、実務上は実印を用い、各相続人の印鑑証明書も添付します。
遺産分割協議書の押印に用いる印鑑には、法律上の制限はありませんが、相続人全員が本人の意思で遺産分割協議を行ったことを確実に示すために、実務では実印が用いられます。
多くの相続手続きにおいても、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書と印鑑証明書が必要とされます。